福島県立相馬農業高校飯舘校
さよなら、校舎。【前編】
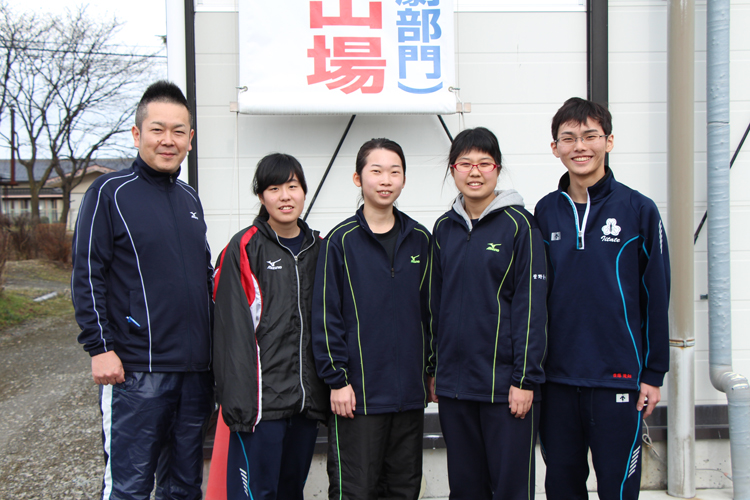
東京駅から始発の新幹線に乗って約1時間30分。福島駅から在来線に乗り換え、ひと駅。冬の北風が吹きすさぶ野ざらしのホームに降り立って、初めて僕は福島の冬の寒さを痛感した。
相馬農業高校飯舘校は、そんな南福島駅から歩くこと徒歩10分強ほどの場所にある。周囲を囲む住宅街を曲がり、幅広の砂利道の先に見える2階建ての小さなプレハブ校舎。正直に言おう、それは校舎という呼び名より、どちらかと言うと、校庭の脇に建てられた部室棟に近いような、そんな小さな小さな建物だった。
生徒数は3学年合計で63名。そこが、あの子たちの「母校」だった。
(Text&Photo by Yoshiaki Yokogawa Assistant by Kanata Nakamura)
全国で瞬いた、飯舘校という光。
あのときの興奮は今でも覚えている。興奮なんて言ったら、勧善懲悪のアクションドラマか何かを想起されるかもしれない。でも、あの感覚は決してそんなわかりやすいものじゃない。もっと静謐で、透明で、でも全身の血流がうねりを上げ、狭い座席にとてもおさまっていられないような高揚に、僕は湧き立っていた。2017年8月2日、第63回全国高等学校演劇大会2日目、ちょうど飯舘校による『-サテライト仮想劇-いつか、その日に、』が幕を下ろした直後のことだ。
『-サテライト仮想劇-いつか、その日に、』は、相馬農業高校飯舘校によるオリジナル作品だ。脚本を書いたのは、顧問の西田教諭(筆名:矢野青史)。登場人物は、飯舘校に通う3人の生徒(ハルカ、サトル、ユキ)。そして教員のイクミ先生。飯舘校は、東日本大震災による福島の原発事故で避難を余儀なくされ、元々校舎が存在した飯舘村から遠く離れること35km、市内の福島明成高校の敷地内に臨時の仮設校舎を建て、そこで授業を行っている。これをサテライト校と呼び、原発事故が発生した2011年時、避難区域に指定された各校は、他校や公共施設のスペースを間借りするかたちで、学校運営を続けた。

あれから6年(全国大会時)、多くのサテライト校が休校していく中、今もサテライト校として運営を継続しているのは、県内ではこの飯舘校のみとなった。時間の経過により、今、飯舘校に通っているのは、本来校舎が存在した飯舘村とは関係のない生徒がほとんど。もっと言えば、「他の市内の高校には入れない」生徒たちが、飯舘校に通っている。仮住まいの校舎に通う、不器用な子どもたち。いつか来るであろう、校舎が元の飯舘村に還るその日を想像し、胸を痛め、想いをぶつけ合う心の襞を描いたのが、この『-サテライト仮想劇-いつか、その日に、』だ。
東北ブロックの代表として、全国の大舞台で凜とした光を放ったあの子たちが、6ヶ月の時を経て、今度は東京でもう一度、『-サテライト仮想劇-いつか、その日に、』を上演すると言う。そのニュースにふれ、たまらなくなった僕はすぐさま取材の連絡を取りつけた。あの子たちがここにいる、ということを少しでも多くの人に知ってもらうために。それは、ほとんど本能に近い使命感だった。
創部2年で東北大会に。その直後に訪れた部存続の危機。
飯舘校演劇部の歴史は、まだ浅い。部ができたのは、西田教諭が着任した2014年末のこと。ハルカ役の菅野千那さん、そしてユキ役の菅野優歩さんは、それから半年後の2015年、入学と同時に演劇部に入部した。まだ自主公演を一度打っただけの、小さな部。もちろん大会に出た経験も一度もなかった。
「あの頃は今とはまったく雰囲気も違っていて。周りもみんな初心者。イチから勉強していかなければいけなかったので、先輩についていくというよりも、自分たちで食いついてしがみついてやっていく、という感じでした」(千那さん)

千那さん、優歩さんに少し遅れてイクミ先生役の髙橋夏海さん(取材日は体調不良のため欠席)も入部。ささやかではあったが、部としてゆっくりと歩みはじめた。今でこそ基礎練習も生徒主体で取り組んでいるが、最初からそんな盤石な体制だったわけではない。特に苦労したのは、練習になかなか人が集まらない、ということだった。
「いちばん少ないときは、ひとりということも。全然まとまりがなくて。とても集団とは言えなかったですね」(千那さん)
それでも少しずつ公演を重ね、経験を積むうちに、演劇の楽しさを知り、責任感に目覚めはじめた。1年目のコンクールでは、『ファントム オブ サテライト~飯舘校の怪人~』で東北大会まで進出。優良賞を受賞した。飯舘校を舞台に、サテライト校に通う現役の生徒と、飯舘村に今も残る元校舎のファントムが出会うファンタジー作品だ。創部2年目、コンクール初参加で東北大会まで上がることは並大抵のことではない。快挙と称えて良いだろう。

ところが、東北大会を終えて、また次の1年に向けてと意気込む矢先、上級生2名が相次いで退部。部に残ったのは、千那さん、夏海さん、優歩さんの1年生3人だけとなった。これからこの部はどうなるんだろう。そんな先の見えない不安が広がる中、残った彼女たちにもう一度大舞台を経験させてあげたい。そう思った西田教諭は、ずっと温めていた伝家の宝刀を抜く決心をした。それが、『-サテライト仮想劇-いつか、その日に、』だった。
小さな教室の中で生きる、少しだけ不器用な子どもたち。
「演劇部をつくったときから、いつかは校舎がなくなる日の芝居はやりたいし、やらなければいけないだろうと思っていたんですよ。でもそれはもっと先の話だろう、と。実際に校舎がなくなると決まったタイミングあたりかなと漠然と考えていました。けど、新年度になっても新1年生の入部はゼロ。もしかしたら今やらないと上演するチャンスさえなくなるかもしれない。そう思って、みんなにこの作品のことを伝えました」(西田教諭)
『-サテライト仮想劇-いつか、その日に、』は、非常にドキュメンタリー性の高い作品だ。いずれこの飯舘校は村に還る。主人公のハルカは、このプレハブ校舎で過ごす最後の1日のことを想像する。校舎がなくなることに、はっきりと苛立ちを示すハルカ。怒りっぽくて、言葉も乱暴な彼女は、実は中学時代、学校に行けなかったという過去を持つ。それは、演じる千那さんも同様だった。

「私の中学では、2つの小学校から生徒が入ってきたんですけど。その中で周りの人に合わせようと気を遣っているうちに、だんだん疲れはじめて体調を崩すうようになって。中学1年の6月くらいからしばらく学校に行かくなりました」(千那さん)
「真面目くん」と揶揄されるサトルも中学までは不登校児だった。演じる後藤滝翔さんが、演劇部に入部したのは、ちょうど2年生に上がる直前の春。そんな中途半端な時期に演劇部へ入ったのも、「環境に慣れるのが苦手」という繊細な性格ゆえのことだった。
「中学の頃、まる2~3年、ずっと人と喋っていない時期がありました。高1のときに部活に入らなかったのも、まずは新しい環境に慣れることに集中したかったから。演劇部には、目をかけてくれている先生から部活動でも始めたらどうだと勧められたのがきっかけで興味を持って。それまでは演劇部と言っても、小学校の学芸会のような、言葉は悪いですけれど、そういう程度の低いものをやっているという偏見がありました」(滝翔さん)

取材にやってきた僕たちを何かと気にかけ、いろいろ部の説明をしてくれたのが滝翔さんだった。滝翔さんは、練習中も同級生の女子に対して敬語で話す。年齢に不似合いなくらい真面目で礼儀正しいその様子からは、とてもコミュニケーションが苦手には見えない。だが、そんな謹厳実直な振る舞いもすべて彼にとっては自分を守るための防御壁だった。
「僕は女性恐怖症なところがあって。だから、女子とは敬語で喋るようにしています。うちの部は僕以外、全員女子。今だから言うと、最初は全然笑っていなかったと思います。みんながワイワイと喋っているときも、僕はボーッと突っ立っているだけで。途中からはどんどん吐きそうになって、体調も崩すようになって、入部してしばらくは練習を休む日が続きました」(滝翔さん)
お芝居をしているときの方が喋りやすい。自分たちの3年間がつまった、演劇部という場所。
黙々とリコーダーの練習を続けるユキ役の菅野優歩さんも、役柄同様、人と話すのが少しだけ苦手な女の子だった。ひとつの質問に対し、じっくり時間を使って考え、ぽつりと短い答えを返す。決して器用と言えるタイプではないと思う。だけど、その言葉は何の嘘も誇張もない、彼女だけの言葉だった。
「私は人と話すのが苦手で。小6のときにいじめられたこともありました」(優歩さん)
そんな校庭の隅に咲く野の花のような少女が、演劇部に入ったのは、演じることが好きだったからだ。

「小さい頃に演技の真似をしていたら、両親に褒められて。それがとても嬉しかったのが、きっかけでした」(優歩さん)
演劇は、人との共同作業だ。コミュニケーションなくして、いい作品はつくれない。人と話すことが苦手な彼女にとってみたら、最も苦手な分野を選んだようにも思えた。だが、そう聞くと、優歩さんは「大変なことはない」と小さく答え、演劇部での思い出を振り返った。
「人が演技をしているのを見て、私が『こうした方がいいね』と言ったら、みんなちゃんと聞いてくれる。そして、その子がちょっと成長する。それが、とても嬉しいです」(優歩さん)
自分が演じているときも同じだ。普段は話をするのが苦手な優歩さんも、お芝居の中では思いのままに話すことができる。
「台詞なら喋りやすい。お芝居をしているときは楽しいです」(優歩さん)
被害者ぶりたくない。『-サテライト仮想劇-』というタイトルにこめた想い。
唯一飯舘村の出身であり、校舎が村に還ることを喜んでいるのが、イクミ先生だ。そのイクミ先生を演じる髙橋夏海さんも、部の中で唯一の飯舘村出身者。この『-サテライト仮想劇-いつか、その日に、』は舞台設定だけでなく、キャラクターそのものも演じる生徒の人物像を投射して描かれている。それは、教諭として、部活の顧問として、近い距離で生徒を見つめ続けてきた西田教諭だからできることだ。
「せっかく去年は東北大会まで行けたのに、今年は地区で終わりましたでは悔しい。せめて県大会までは上がりたかったので、短い期間の中で良いものをつくろうと思ったら、自分たちに近い役の方がいいだろうと考えました」(西田教諭)
まずは2年になってすぐの春の発表会で、プロトタイプ版を上演。当時は「-サテライト仮想劇-」というフレーズはなく、タイトルは『いつか、その日に、』だけだった。「-サテライト仮想劇-」を正式に冠するようになったのは、11月の地区大会から。現実ではなく、仮想劇なのだ、ということを強調したのには、飯舘校らしい信念があった。

「あまり被害者ぶっちゃいけないなって。それは、震災を題材にお芝居をつくるとき、必ずついて回る危険性というか。この福島という土地で悲しい想いをしている人たちがいることを伝えることはもちろん大事だと思います。けれど、だからと言って、『自分たちの校舎が壊されるんだ』と被害者面をすることで、お客さんから涙をもらうようなことは、この演劇部ではしたくなかった。僕らにもそれぞれ事情があってこの学校に来ているわけで。それを被害者として捉えられてしまうと、何かいやらしいような気がしたんです」(西田教諭)
実際、千那さんにしても、優歩さんにしても、滝翔さんにしても、いわゆる全日制の大規模な高校に通うことは難しかった。サテライト校は、そんな生徒のための受け皿として機能している面もあった。
「言ってみれば、ここにしか来られなかった子たちです。このプレハブ校舎がいつかなくなることは、見ればわかること。それをわかった上で入学している。だから、被害者のような顔はしたくなかった。そのことを改めてアピールしておくために、『-サテライト仮想劇-』と頭につけることにしました」(西田教諭)

春から長い時間をかけて練り込まれた同作は地区大会でも好評を博し、無事に目標だった県大会へと駒を進めた。しかし、ここで飯舘校演劇部は大きな賭けに出る。地区大会から県大会までの期間は、約3週間。その短い間に、台本を大幅に変更することを決めたのだった。
>> 後編へ続く
