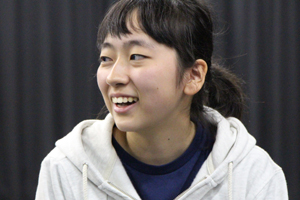学校法人追手門学院 追手門学院高校
変わり続ける日々の中で。【前編】

人生は、変化の連続だ。進学、就職、卒業、転職、結婚、出産、育児、介護。そんなライフイベントの数々を挙げるまでもなく、延々と同じことの繰り返しのような毎日でさえ小さな変化の積み重ねによって成り立っている。いくつかの原子が結びつき、化学変化を起こしていくように、変わり続ける日々の中で、私たちは変化とどう付き合えばいいのだろうか。その問いに1年間、真摯に向き合い続けた高校生たちがいる。これは、とある高校生たちの変化をめぐるいくつかの物語だ。
(Text&Photo by Yoshiaki Yokogawa)
40年の伝統の終わり。そして、新しい歴史の始まり。
 追手門学院高校演劇部といえば、全国大会の出場経験も持つ古豪だ。40年に渡って同校を率いた阪本龍夫教諭は、府内で高校演劇に携わる教員なら知らない者はいないと言われるほどの有名人。かつて近畿大会9年連続出場を記録するなど、名門校としてその名を轟かせた。その阪本教諭が定年により同校を去ることになったのは、2015年春のこと。この転機こそが、これから始まる追手門学院高校演劇部――通称“追演”の変化をめぐる物語の始まりだった。
追手門学院高校演劇部といえば、全国大会の出場経験も持つ古豪だ。40年に渡って同校を率いた阪本龍夫教諭は、府内で高校演劇に携わる教員なら知らない者はいないと言われるほどの有名人。かつて近畿大会9年連続出場を記録するなど、名門校としてその名を轟かせた。その阪本教諭が定年により同校を去ることになったのは、2015年春のこと。この転機こそが、これから始まる追手門学院高校演劇部――通称“追演”の変化をめぐる物語の始まりだった。
「阪本先生は人のことをちゃんと見てくれる人。体調不良が多くて部活を休みがちだったときも、声をかけてくれた。先生が好きだったから、いなくなるのはやっぱり寂しかったです」
 3年の小阪は恩師との別れをそう振り返る。まだティーンエイジャーの部員たちにとって、阪本教諭とは祖父と孫ほどの年齢差。「怖くて厳しかった」と言う者もいれば、「頑固で偏屈」と評する者もいる。それでも、断言できることは、「阪本教諭がいなければ追演はない」ということだった。2015年3月、部員たちが恩師との最後の舞台として選んだのは、キャラメルボックスの『不思議なクリスマスのつくりかた』。充実感と共に幕を閉じた3年生は、4月を迎え、新入生歓迎公演を行うにあたって、もう一度、阪本先生とつくった『不思議なクリスマスのつくりかた』を上演しようと決めていた。
3年の小阪は恩師との別れをそう振り返る。まだティーンエイジャーの部員たちにとって、阪本教諭とは祖父と孫ほどの年齢差。「怖くて厳しかった」と言う者もいれば、「頑固で偏屈」と評する者もいる。それでも、断言できることは、「阪本教諭がいなければ追演はない」ということだった。2015年3月、部員たちが恩師との最後の舞台として選んだのは、キャラメルボックスの『不思議なクリスマスのつくりかた』。充実感と共に幕を閉じた3年生は、4月を迎え、新入生歓迎公演を行うにあたって、もう一度、阪本先生とつくった『不思議なクリスマスのつくりかた』を上演しようと決めていた。
しかし、部員たちの前に現れたある人物が、彼らの日常を根底から覆す。それが、新顧問のいしいみちこ教諭だった。
嵐の訪れ。ある日突然すべてが変わった。
いしい教諭は、五反田団の前田司郎や飴屋法水など豪華なアーティストを招いての演劇授業で注目を集める福島県立いわき総合高校の設立メンバー。同校演劇部を全国大会出場校にまで育て上げた手腕は高く評価されている。その指導力を見込まれ、追手門学院高校が2014年より新設した表現コミュニケーションコースの教員に着任した。そんな“未知なる存在”が、阪本教諭の去った追演の新しい顧問だったのだ。
 「4月にいしい先生との顔合わせがあって。その時から噛みついていこうって決めてました」
「4月にいしい先生との顔合わせがあって。その時から噛みついていこうって決めてました」
3年の松岡は大胆にもそう腹の内を明かす。その言葉の裏には、あるエピソードがある。
新体制を迎えるにあたって、3年生たちは事前に話し合いの場を設けた。そこで、たとえ顧問が変わって作風が変わっても、自分たちは自分たちのやってきた演出でやっていこう。そうみんなで決めたのだった。しかし、その結束は、嵐を前にいとも容易く吹き飛んだ。
いしい教諭は、彼らが「普通」と思っていた部の習慣について次々と指摘をした。
――何で全員揃えて「はい!」って返事をする? 気持ち悪いよ? 軍隊みたい。
――部活終わりのミーティングで、座る時みんなで「失礼します」って言うけど、何でそれ言うの? 考えて言ってる?
――何でお揃いの服を着るの? 見た目だけ揃えても一致団結できるわけじゃないよ?
かつての卒業生がデザインしてくれたクラブTシャツを、いしい教諭はそう言ってのけた。
「新歓も『不思議なクリスマスのつくりかた』をするつもりだったんですけど、入ったばかりの1年生に2時間のお芝居は長すぎるって言われてしまって…」
部員たちの困惑をよそに、いしい教諭の改革はついに“聖地”にまで及んだ。追演の練習場所は、代々のOBOGの汗と涙が染み込んだ体育館の舞台。それが専用の演習室に取って代わった。想い出も愛着もあるとっておきの場所を、部員たちはある日突然失ってしまったのだ。
空中分解の危機。バラバラになった追演の絆。
「私は阪本先生に思い入れがあった分、いしい先生のやり方は全然受け入れられなかった。『不思議なクリスマスのつくりかた』は最後に阪本先生とやった作品やったから、やっぱり新歓でもやりたかった」
そう惜しむ小阪とは対照的に、中立の立場として部をまとめようとしていたのが、部長の森口だった。そのバランス感覚を見込まれ、阪本教諭から部長に指名された森口は、生徒代表として何度もいしい教諭から直接話を聞いた。
「いちばんいしい先生と話をしていたのが、私でした。いしい先生は確かにもっともなことを言っている。だから私は“変化を動かす側”の人間として、伝統と変化の結び目になろうって決めたんです」
いしい教諭の狙いは、決して旧体制の否定ではない。たとえば「失礼します」の挨拶についても、誰に対して「失礼」なのか。顧問と部員の間にヒエラルキーが存在するのか。そう疑問に感じたから、わざわざ言う必要はないと指摘した。クラブTシャツも、表現する人間が人と合わせたものを着ることに、それも10代の若々しい高校生には少し重い黒のTシャツを着ることに違和感を持ったから、「もっと明るい色にしようよ」と提案した。そこにある「普通」に対して何も思考しない硬直状態の感性を解きほぐすことが、一緒に演劇をつくる上でまず必要だと、いしい教諭は思ったのだ。
森口はいしい教諭の想いを伝え、時には橋渡しとなって他の部員といしい教諭との接点をつなぐことで、少しずつ追演を変えていく。同じく3年の池田が語る。
「最初は急に来て、“ここがダメ!”って一方的に言われた印象しかなくて、いしい先生には反発する気持ちがありました。でも、森口に誘われて直接話をしてみたら、決して自分がやりたいから押し通しているわけじゃなくて、ちゃんと私たちのことを思いやってくれているんだということがわかった。それで、阪本先生時代の部活も好きやから嫌なところもあるけれど、変わっていくことに慣れていかないといけないのかなと考えるようになりました」
徐々に広がるいしい教諭を支持する声。しかし、皮肉にもそれは部内の亀裂をさらに深める結果となった。
 「いしい先生のことが受け入れがたいというよりも、今までのかたちでやろうって話になってたのに、コロコロといしい先生に傾いた人たちの態度が気に食わなかった」
「いしい先生のことが受け入れがたいというよりも、今までのかたちでやろうって話になってたのに、コロコロといしい先生に傾いた人たちの態度が気に食わなかった」
そう松岡が本音をこぼせば、小阪も苦い表情を浮かべる。
「みんながどんどん阪本先生のことを忘れていっちゃうような気がして、それで最後の方はちょっと意地みたいになって、阪本先生の演出でやりたいって言ってました」
話し合いの末、最終的に『不思議なクリスマスのつくりかた』はいしい教諭の意見を採用し、合間の劇中劇のみを演じる短縮バージョンとして上演されることとなった。全員が納得した結論ではない。お互いにくすぶった気持ちを抱えながら、新・追演の1年が始まった。
新しい演劇との出会い。広がる戸惑いと好奇心。
 ここで改めて長年追演を牽引した阪本教諭の作風スタイルを説明すると、部員曰く「男臭い」芝居。照明、音響、舞台美術と裏方にも力を入れ、人間の内面を劇的に描くクラシカルな演劇手法で知られていた。戯曲も生徒・顧問創作はもちろんのこと、野田秀樹ら有名作家の作品にも意欲的に取り組む。
ここで改めて長年追演を牽引した阪本教諭の作風スタイルを説明すると、部員曰く「男臭い」芝居。照明、音響、舞台美術と裏方にも力を入れ、人間の内面を劇的に描くクラシカルな演劇手法で知られていた。戯曲も生徒・顧問創作はもちろんのこと、野田秀樹ら有名作家の作品にも意欲的に取り組む。
一方、いしい教諭は、大別するなら「現代口語演劇」と呼ばれる、青年団主宰の平田オリザの流れを汲む、日常的な口語体を用いた演技が特徴だ。同じ演劇というカテゴリーではあるが、毛色はまったく異なる。6月に入り、いしい教諭がかつて指導したいわき総合高校の作品をDVDで鑑賞した追演メンバーは「大阪の高校演劇にはないタイプ。やったことがないだけにワクワクした」と頬を赤く染める一方、「装置を全然使わないので、1・2年でやってきたことが全然活かされされない」と戸惑いも見え隠れした。
「“ラーメンとケーキ、どっちがおいしい?”って聞かれるようなもの。つくり方も全然違うし、どっちがどっちとか比べられない」
そんな松岡の一言が、彼らの混乱と困惑を最も的確に表していた。
そしてHPFへ。自分たちの身近なドラマを作品にする。
大阪府の高校演劇では7月末から8月上旬にかけてHPF(大阪高校演劇祭)という演劇フェスティバルが開催される。参加に向けてのミーティングで、いしい教諭がある提案をした。それが、“阪本教諭が去って揺れ惑う自分たちの変化を作品にする”というものだった。あらかじめ固定のテキストを用意するわけではなく、エチュードをもとにひとつの物語を折り重ねていく。それは、追演が今まで体験したことのない作劇法だった。
 「阪本先生の時もエチュードはやっていたけど、その時のエチュードはテレビドラマのような、いわゆるドラマらしいもの。でも、いしい先生は身近にあるドラマを大切にしていて、私たちの心の動きをカタチにすることを求められた。そんなの意識したことなんてなかったから、どうすればいいか全然わかりませんでした」
「阪本先生の時もエチュードはやっていたけど、その時のエチュードはテレビドラマのような、いわゆるドラマらしいもの。でも、いしい先生は身近にあるドラマを大切にしていて、私たちの心の動きをカタチにすることを求められた。そんなの意識したことなんてなかったから、どうすればいいか全然わかりませんでした」
3年の池田がそう述懐する。ひとつ案が出てもそれを1本のエチュードにまで広げていけない。なぜなら、自分たちがその時に何を感じたのか、そこで自分にどんな変化があったのか、これまで明確に言語化する機会などほとんどなかったから。いくら話し合いの場を持っても、それを表現に昇華するだけの手立てをまだ体得していない追演は、未知なる作劇法に行きづまるばかりだった。
言えなかった本当の想い。守りたかった大事な居場所。
 そんな悪戦苦闘を、どこか客観的に見つめていたのが、3年の松岡だ。松岡はエチュードを重ねる部員たちを見ながら、「こういう話をやれば面白いエチュードになるんじゃないか」というアイデアを早い段階から隠し持っていた。けれど、どうしてもそれを話す気にはなれなかった。自分たちのやり方を貫こうと約束したのに、あっさり鞍替えした仲間たちに心を開けなかったからだ。普段はムードメーカー的役割を担うことの多い松岡だが、その内面は複雑で、これまで築き上げたお調子者のキャラクターを変えてまで自分の葛藤を明かすことに抵抗を抱えていた。
そんな悪戦苦闘を、どこか客観的に見つめていたのが、3年の松岡だ。松岡はエチュードを重ねる部員たちを見ながら、「こういう話をやれば面白いエチュードになるんじゃないか」というアイデアを早い段階から隠し持っていた。けれど、どうしてもそれを話す気にはなれなかった。自分たちのやり方を貫こうと約束したのに、あっさり鞍替えした仲間たちに心を開けなかったからだ。普段はムードメーカー的役割を担うことの多い松岡だが、その内面は複雑で、これまで築き上げたお調子者のキャラクターを変えてまで自分の葛藤を明かすことに抵抗を抱えていた。
そんな頑なな松岡の心を変えたのは、やはり追演に対する想いだった。
「こういうエチュードをするなら、本当に心の底から思っていることでないと話にならない。僕も話したくないことがあるように、多かれ少なかれみんなにも話したくないことはあるはず。なら自分が話したら周りも話してくれるかなって。ここで話さないと、もう話す機会もないやろうと思って、みんなの前で話をすることを決めました」
 それが、HPFで上演した『変化をめぐる習作のいくつか』でも採用された“掃除”に関するエピソードだった。松岡は入部間もない1年の頃から、ずっと練習場所だった体育館の舞台を朝から掃除するのが習慣だった。そして、その習慣は練習場所が変わり、誰も体育館の舞台を使わなくなった今もずっと続いていた。
それが、HPFで上演した『変化をめぐる習作のいくつか』でも採用された“掃除”に関するエピソードだった。松岡は入部間もない1年の頃から、ずっと練習場所だった体育館の舞台を朝から掃除するのが習慣だった。そして、その習慣は練習場所が変わり、誰も体育館の舞台を使わなくなった今もずっと続いていた。
もちろん新しい演習室の方がずっと広々として機能的だ。体育館で練習をしている時は、よく他の運動部の音で自分たちの声がかき消された。でも、この舞台の上で、40年間、それこそ顔も知らないOBOGたちもみな練習に励み、演劇を愛した。自分たちの2年間の思い出だって、この床材の木目にまで染みついている。そう簡単に捨て去ることなんできない。
人知れず、もう使われることのない、かつての“聖地”をたったひとりで毎朝掃除し続ける松岡。それは、普段の明るさからはうかがい知れない、繊細で義理深い横顔だった。
変わり始める部員たち。そして、ドラマは動き出す。
 「松岡先輩はずっと自分の想いを言ってこなかった。その先輩の本当の気持ちを知れたのは大きかった」
「松岡先輩はずっと自分の想いを言ってこなかった。その先輩の本当の気持ちを知れたのは大きかった」
2年の河崎は、松岡の告白をそう受け止めた。松岡が投げた石は、確かに湖面に波紋を広げた。指定校推薦を狙う3年の小阪も部活と勉学の両立に厳しさを抱えていた。その不安を正直にみんなの前で打ち明けた。部長の森口は『変化をめぐる習作のいくつか』を「みんながいちばんクラブのことを考えてつくった作品」と位置づける。
「普段からミーティングであんまり喋らなかった子が心を開いて話してくれるようになったり。自分たちのことを作品にすることで、男女とか先輩後輩関係なく、みんなの距離が近づくようになった気がします」
「今までずっと裏方をやっていた僕は、どこかスタッフワークのことをやってれば良いという感覚で、劇をつくることに積極的に関与してこなかった。でも自分の意見を言って、それが劇に採用される面白さを知って、どんどんみんなとコミュニケーションをとるようになりました」
対立。混乱。葛藤。孤立。いしい教諭のもたらした変化によって、いくつものヒビが走った追演。だが、その割れ目から小さく、でも確かに、新しい芽が生まれようとしていた。
>> 後編へ続く