大阪府立東住吉高校
もうこんな仲間は、二度とできない。【前編】

これまで約20年に渡って、大阪の高校演劇生の聖地として、様々なドラマを見守り続けてきたよみうり文化ホール。その長い歴史が、昨年、幕を下ろした。何千人にも及ぶ高校生の汗と涙が染みこんだ舞台に最後に立ったのが、東住吉高校演劇部だ。矢継ぎ早に飛び出すネタの応酬で、台詞が聞き取れないほどの爆笑を巻き起こしたヒガスミ演劇。だが、その過程は地区大会本番3日前にようやく台本が完成した、文字通りの「突貫工事」だった。彼らに何が起こったのか。全員一丸となって駆け抜けた怒濤の1ヶ月を追った。
(Interview by Ai Miyazaki Text&Photo by Yoshiaki Yokogawa)
悲願の近畿出場へ。避けて通れなかった「創作」の壁。
もともと人一倍豊かな感受性の持ち主。これまでも演劇部のことを口にするたびに、人目もはばからず男泣きをする場面はしばしばあった。しかし、その日の涙は違った。抱え続けてきた苦しい想いを吐き出すような、大号泣。地区大会本番2週間前、練習中での出来事だった。
話は、少し時間を遡る。
東住吉高校――通称・ヒガスミは、日本で唯一の芸能文化科を擁する公立高校だ。校内にはプロ級の設備が整った実習棟を有し、県外からも演劇や芸能に関心のある生徒が集う。しかし、そんな恵まれた練習環境とは裏腹に、近年は地区敗退が続き、思うような結果が出せずにいた。歯がゆい現状を打ち破ったのが、2011年。まだ戸梶らが1年生だった時のことだ。久々の府大会進出を果たし、審査員特別賞を獲得した。次こそは近畿へ。悲願達成のために欠かせないのが、オリジナル台本の創作だった。
「もともとは私が書く予定だったんです。だけど、いざ書こうと思ったら、なかなか思うように進まなくて。そこに家庭の事情も重なって、結局途中で諦めることになってしまいました」
2年の大賀が申し訳なさそうに俯く。夏のプレゼンテーションでは、候補者の中から彼女の作品が選ばれた。しかし、9月の文化祭を前に頓挫。ピンチヒッターとして躍り出たのが、戸梶だった。
沸き上がる焦りと後ろめたさ。言えなかった本当の気持ち。
とは言え、ここ最近の公演は既成作品のみ。台本を書いた経験はゼロだった。プロットの立て方もト書きの書き方さえわからない。それでも、戸梶はがむしゃらになって書き上げた。その名も『ヒーローカスタネット』。台詞回しや展開の奇抜さに特有のセンスは光るものの、本人の厭世観がむきだしにつめこまれた作品を理解しきれる者は少なかった。
「正直、これでやるのかと思いました」
 2年の大村が苦笑いする。しかし、他に書き手はいない。今更台本にケチをつけても、書き直している時間はない。一刻も早く練習を進めなければという焦りと、自分には台本を書く力がないという後ろめたさが、それぞれの本音に封をさせた。チェーンの外れたタイヤで走り出したヒガスミ演劇部は、ただ空回りしたまま、崩壊の時を待つだけだった。
2年の大村が苦笑いする。しかし、他に書き手はいない。今更台本にケチをつけても、書き直している時間はない。一刻も早く練習を進めなければという焦りと、自分には台本を書く力がないという後ろめたさが、それぞれの本音に封をさせた。チェーンの外れたタイヤで走り出したヒガスミ演劇部は、ただ空回りしたまま、崩壊の時を待つだけだった。
このまま続けるか、台本を変えるか。涙の緊急ミーティング。
 転機は、本番2週間前。練習を見に来たOB・OGのコーチに、役者が1人ひとり呼び出された。自分の役柄について、作品の意図について、コーチの詰問に満足な返答をできる者は誰もいなかった。台本のことをまるで理解していない人間が、お客様の心を動かす芝居をつくれるのか。本当にこの台本のまま大会に出場するのか。厳しく問いただされた2年は、部員全員を集めて緊急ミーティングを開いた。
転機は、本番2週間前。練習を見に来たOB・OGのコーチに、役者が1人ひとり呼び出された。自分の役柄について、作品の意図について、コーチの詰問に満足な返答をできる者は誰もいなかった。台本のことをまるで理解していない人間が、お客様の心を動かす芝居をつくれるのか。本当にこの台本のまま大会に出場するのか。厳しく問いただされた2年は、部員全員を集めて緊急ミーティングを開いた。
「この台本の何がダメなのかわからない」
「正直、私はこの台本はやりたくない」
「じゃあ誰が台本を書き直すのか」
「いっそ既成に戻した方がいいか」
台本をめぐって意見が飛び交う中、ついに戸梶は嗚咽をこらえきれなくなった。
本当は、ずっと苦しかった。文化祭への参加を返上して、台本を書くという孤独な作業を、ひとり耐え抜いてきた。書きたいことは、きっとあった。けれど、書けば書くほどにどんどんまとまりがなくなっていった。自分の書きたいものは何か。それさえももうわからなかった。ボロボロとこぼれ落ちるのは、自分の力のなさを責める涙だった。
「今思えば、あの時の台本は自分の愚痴の塊だった。人に見せるものじゃない。ただの僕の自己満足でしかありませんでした」
だが、その頃はそんな本音さえ言えなかった。誰かに相談したからと言って、どうにかなるものでもない。自分を気遣う周囲の優しさも「慰めのようにしか思えなかった」と戸梶は吐露する。
一方、本当のことを言えなかったのは、戸梶だけではなかった。音響に就くことになった大賀は、戸梶の書き上げた台本を読んで「何が言いたいのか方向性が見えない」と不安を感じていた。
 「だけど、一度投げ出した自分にそんなこと言う資格はないと思っていました。とにかく自分のできることをやろうとひたすら選曲を進めていたんですが、“お前は自分のことさえできてればいいのか”って、コーチに言われてしまって。自分に何ができるのか、何をしなければいけないのか、あの頃の私はまったくわからなくなっていたんです」
「だけど、一度投げ出した自分にそんなこと言う資格はないと思っていました。とにかく自分のできることをやろうとひたすら選曲を進めていたんですが、“お前は自分のことさえできてればいいのか”って、コーチに言われてしまって。自分に何ができるのか、何をしなければいけないのか、あの頃の私はまったくわからなくなっていたんです」
相手のことを思いやるつもりで、ずっと口をつぐんでいた。けれど、それは本当の意味で相手を思ってのことではなかった。ただ、衝突を避けるため。ただ、自分の自信のなさから目をそらすため。本音を隠して、なし崩しにしようとしていただけだった。
ぶつかり合う想い。全員で決めたひとつの答え。
「もう時間がない。新入生歓迎会でやった舞台をやろう」
大村はそう提案した。人一倍、近畿大会への憧れが強かった彼女の、苦肉の策だった。過去公演の焼き直し。それは、自分たちの負けを認めたようなものだった。だけど、今のままでは絶対に上には行けない。一縷の望みを託した大村の意見に、全員が流されようとしていた。
口火を切ったのは、2年の大窪だった。
 「僕は戸梶の台本が好きだったんです。台詞も、世界観も、こんなの見たことがないってくらい大好きで。戸梶の台本なら絶対に行ける。そう信じていました」
「僕は戸梶の台本が好きだったんです。台詞も、世界観も、こんなの見たことがないってくらい大好きで。戸梶の台本なら絶対に行ける。そう信じていました」
戸梶の台本でやりたい。大窪は、みんなに訴えかけた。呼吸もままならないような激しい涙。大窪は、その場にうずくまり、ごうごうと泣いた。その姿に、戸梶は何も言えず、また涙した。先輩のやりとりを聞いていた1年も次々と泣き出した。その中で、大賀はただ黙りこくっていた。
「大村の気持ちも、大窪の気持ちも、よくわかる。よくわかるからこそ、どうしたらいいのかがわからなかった」
正解は、わからない。だけど、前に進むためには答えを決めなければいけなかった。泣いて、悩んで、苦しんで、最後に出した答えはひとつだった。
もう一度、戸梶の台本をゼロから書き直して、やろう――
本番まで残り14日。一生忘れられない2週間が、始まった。
本番2週間前からの台本制作。迫りくる時間との戦い。
「とは言え、間に合うのかなという不安はありましたね」
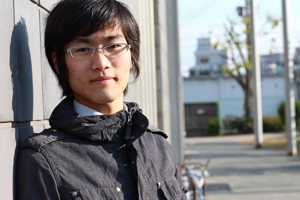 2年の中野が当時の心境をそう振り返る。台本の全面書き直し。当然、キャストもスタッフもゼロからのスタートだ。自分たちは何を伝えたいのか。考えた末に出た結論は、今の自分たちのことをありのままお芝居にするということだった。戸梶は言う。
2年の中野が当時の心境をそう振り返る。台本の全面書き直し。当然、キャストもスタッフもゼロからのスタートだ。自分たちは何を伝えたいのか。考えた末に出た結論は、今の自分たちのことをありのままお芝居にするということだった。戸梶は言う。
「自分の悩みや苦しみを人に話したところで、わかってもいないのに“わかるよ”と労わられるのが、すごく嫌いだったんです。だけど、心の奥底ではわかってほしい気持ちがあった。そういう葛藤を、新しい台本にはつめこみました」
主人公・三原は、バラバラになった演劇部をもう一度ひとつにするため、台本づくりにチャレンジする。しかし、一向に完成しない台本に、むしろ部員たちの心はさらに離れていく。周囲からのプレッシャーに押し潰され、精神を崩壊する三原は、そのまま戸梶の姿に重なる。
追いつめられた戸梶の孤独な執筆作業を支えたのが、大賀だった。
「もとはと言えば、最初に台本を途中放棄した自分のせい。だから、ずっと迷惑をかけた後ろめたさがありました。そんな自分に何ができるのか。考えて、考えて、出た答えは、何ができるとかじゃなくて、ただ戸梶を支えたいということでした」
それは、罪悪感とも責任感とも違う。仲間への純粋な想いだった。戸梶が書き殴った荒削りの台本を、大賀がひとつひとつ丁寧に整えていく。自分たちが書かなければ、練習が進まない。信じて待ってくれている仲間のために、ふたりは毎日図書室にこもって、台本書きに明け暮れた。
信じてくれる人がいたからできた。感謝と絆の2週間。
 1日、また1日と時間が過ぎていく中で、少しずつ台本ができていく。役者はできたところから台詞を頭に叩き込んでいく。演出である戸梶は台本書きと塾通いでほぼ不在。その分、全員で支え合って場面を仕上げていった。台本が本当に完成するのかはわからない。本番までにお客様に見せられるものができるのかもわからない。恐怖と焦りの2週間だったはずだ。
1日、また1日と時間が過ぎていく中で、少しずつ台本ができていく。役者はできたところから台詞を頭に叩き込んでいく。演出である戸梶は台本書きと塾通いでほぼ不在。その分、全員で支え合って場面を仕上げていった。台本が本当に完成するのかはわからない。本番までにお客様に見せられるものができるのかもわからない。恐怖と焦りの2週間だったはずだ。
しかし、当時を振り返る彼らの表情はどこまでも清々しく、爽快な笑顔に満ちている。それは、全力でやりきった自分たちに対する誇りと達成感の表れのように見えた。
結局、台本が完成したのは、本番3日前。
徹夜続きの戸梶は、何度も嘔吐を繰り返した。タイトルは、『僕らはいつも五時帰り』。様々な事情で、本気で部活に打ちこめない部員たちの等身大で伸びやかな青春グラフティ。「自分の自己満足でしかなかった」と言い捨てた最初の台本と何が違うのか。戸梶は、その質問に間髪入れずに即答した。
「支えてくれる人がいたこと、ですね」
自分ひとりで書き上げた台本じゃない。みんなが、少しずつ力をくれた。直接ペンをとっていない者も含めて、キャストも、スタッフも、2年も、1年も、一緒にいてくれたみんながいたからできた台本だ。
たった2週間の間に合わせの芝居がどう評価されるのか。それは幕が開かなければわからない。やれることは、あとは全力で楽しむだけ。血を吐く想いで駆け抜けた2週間の真価が問われる時が来た。
>> 後編へ続く

